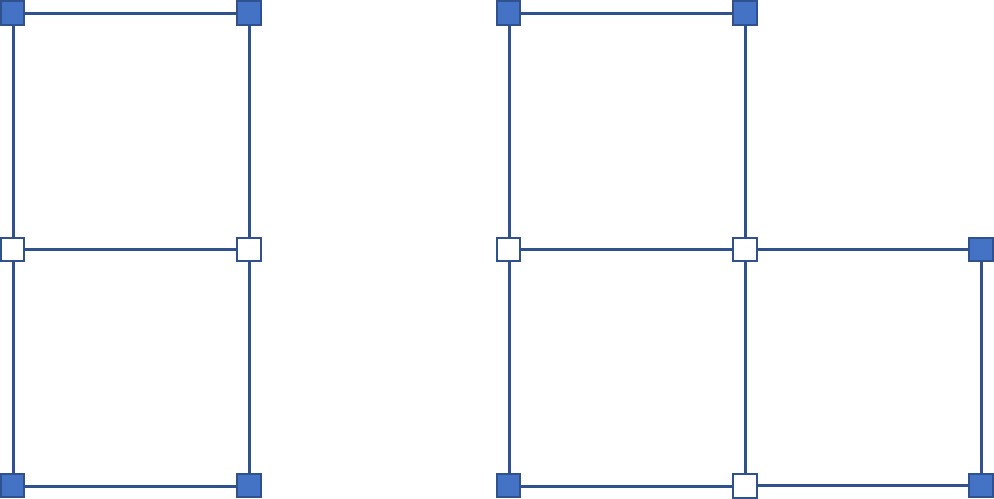許容応力度計算とは -その4-
(平19国交告第594号 第2)
2022.09.18
許容応力度計算の方法
(平19国交告第594号 第2)
- 平19国交告第594号 では、構造計算に用いる数値の設定方法と、荷重・外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法などについて規定されています。
- 平19国交告第594号 第2では、令第81条第一号の規定に基づき、許容応力度計算を行う場合の荷重・外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法が定められています。
荷重・外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法
(平19国交告第594号 第2 第三号)
- 平19国交告第594号 第2 第三号では、第一号に加えて検討しなければならない計算について規定されています。
- ただし、特別な調査または研究によって同等以上に構造耐力上安全であることを確かめることのできる計算を行う場合は、それぞれの計算の適用を除外することができます。
耐力壁を有する剛接架構に作用する応力の割増し
(平19国交告第594号 第2 第三号 イ)
- 架構の一部に設けた耐力壁の剛性が高い場合、地震力によって剛接架構の柱に生ずる応力が非常に小さくなる場合があります。
- しかしながら、耐力壁の剛性は正確な評価が困難であり、過大な評価をした場合は、剛接架構に生ずる応力を過小評価してしまうことを勘案して、剛接架構の柱に一定の耐力を確保することが求められています。
- このとき、せん断力に加えてせん断力に見合う曲げモーメントも柱が負担できるようにする必要があります。
- 具体的には、以下の検討を行う。
- 耐力壁を有する地上部分の剛接架構において、地震力作用時にある階の耐力壁が負担するせん断力の和がその階の層せん断力の1/2を超える場合に、その階の剛接架構部分の柱(耐力壁の端部となる柱は除く。)それぞれについて、当該柱の支える重量に一次設計用地震層せん断力係数を乗じた値の25%(Co=0.05 に相当)以上のせん断力が作用した際の応力度が、短期許容応力度以下となることを確かめること
4本柱等冗長性の低い建築物に作用する応力の割増し
(平19国交告第594号 第2 第三号 ロ)
- 4本柱の建築物等の架構の不静定次数が低い建築物は、少数の部材の破壊で建築物全体が不安定となる恐れがあり、構造計算にあたっては、慎重な検討が必要です。
- 出隅部の柱がその階が支える常時荷重の20%以上の荷重を支持する場合について、張り間方向および桁行方向以外の方向についても水平力が作用するものとして建築物全体での許容応力度計算を行うことが求められています。
- このとき、規定の趣旨は上部構造に一定の耐力を確保することであるため、地下部分については上部構造の耐力の確保に関連する部分(例えば、柱脚における引抜きなど)に限って、規定に基づく追加的な割増しの検討が必要です。
- なお、地上3階以下かつ高さ20m以下の建築物は、実態上問題になることが少ないものとして、検討対象から除外されています。
- 具体的には、以下の検討を行う。
- 地上4階以上または高さ20mを超える建築物において、いずれかの階の出隅部の柱が常時荷重の20%以上の荷重を支持する場合に、張り間方向および桁行方向以外の方向(通常の場合は、斜め45度方向でよい)についても、水平力が作用するものとして建築物全体での許容応力度計算を行うこと。
- ただし、これら斜め方向の検討に代えて、張り間方向・桁行方向それぞれの方向について、一次設計用地震層せん断力係数を1.25倍(Co=0.25 以上)とした検討とすることができる。
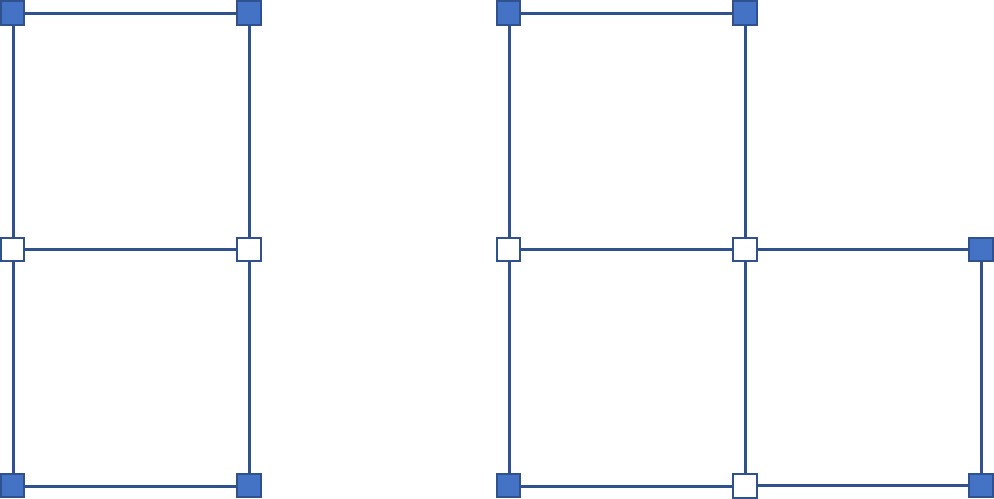 検討対象となる出隅部の柱(■印位置)の例
検討対象となる出隅部の柱(■印位置)の例
水平震度による突出部分に作用する応力の割増し
(平19国交告第594号 第2 第三号 ハ)
- 建築物の屋上から突出する部分(昇降機塔など)または建築物の外壁から突出する部分(屋外階段など)は、水平震度 1.0Z 以上の水平力により、当該部分と当該部分が接続する部分に生ずる応力を算定することが規定されています。
- また、屋上から突出する部分の高さが2m以下の場合には、振動の励起が生じにくいものとして、検討対象から除外されています。取り付け部からの高さが2m以下の部分に対しては、別途屋上から突出する建築設備等の計算基準(平12建告第1389号)が適用されます。
- 入り隅部等で二方向に有効に拘束されている屋外階段など、地震時におおむね一体として挙動することが想定できる部分は、規定の適用外とすることができます。
- さらに、突出部分については、本体架構の変形に追従できることを確かめる必要があります。
- なお、地上3階以下かつ高さ20m以下の建築物は、実態上問題になることが少ないものとして、検討対象から除外されています。
- 具体的には、以下の検討を行う。
- 例えば、突出部分を局部震度で、本体架構を地震力で、それぞれ分割して検討するなどの方法が考えられる。
鉛直震度による突出部分に作用する応力の割増し
(平19国交告第594号 第2 第三号 二)
- 片持ちバルコニー等の外壁から突出する部分について、規模の大きな張り出し部分は、鉛直震度 1.0Z 以上の鉛直力により、当該部分と当該部分が接続する部分に生ずる応力を算定することが規定されています。
- なお、例えば先端部分を支持する柱等を設け、鉛直方向の振動の励起を防止する措置を講ずることができれば、突出部分に該当しないものとして検討を不要とできます。
- また、外壁から突出長さが2m以下の場合には、振動の励起が生じにくいものとして、検討対象から除外されています。
- 具体的には、以下の検討を行う。
- 例えば、短期の許容応力度の値が、長期の許容応力度の値の 1.5倍であることを考慮して、常時荷重を 1.33倍(=鉛直荷重が常時荷重の 2倍 / 許容応力度が長期の 1.5倍)して長期の許容応力度の確認を行うことが可能です。
積雪後の降雨の影響を考慮した応力の割増し
(平19国交告第594号 第2 第三号 ホ)
- 規模が比較的大きい緩勾配の屋根部分について、積雪後の降雨の影響を考慮して、積雪荷重に割増し係数を乗ずることが定められています。
- 次の内容に該当する建築物は、割増し係数を積雪荷重に乗じて、令第82条各号の計算を行う必要があります。(3.及び4.に該当する屋根部分を『特定緩勾配屋根部分』といいます。)
- 多雪区域以外の区域にある建築物
- 垂直積雪量が15㎝以上
- 屋根の勾配が15度以下
- 屋根の最上端から最下端までの水平投影長さが10m以上
- ただし、屋根版がRC造またはSRC造の場合には、適用の対象から除外されています。
- α=0.7+√dr / μb・d
- α:割増し係数(α≧1.0とする)
- dr:平19国交告第594号 第2 第三号 ホ 表に規定の数値(m)
- μb:屋根形状係数
- d:垂直積雪量(m)
≪ BACK ≪ 許容応力度計算とは -その3-
許容応力度計算とは -その4-<br>(平19国交告第594号 第2)